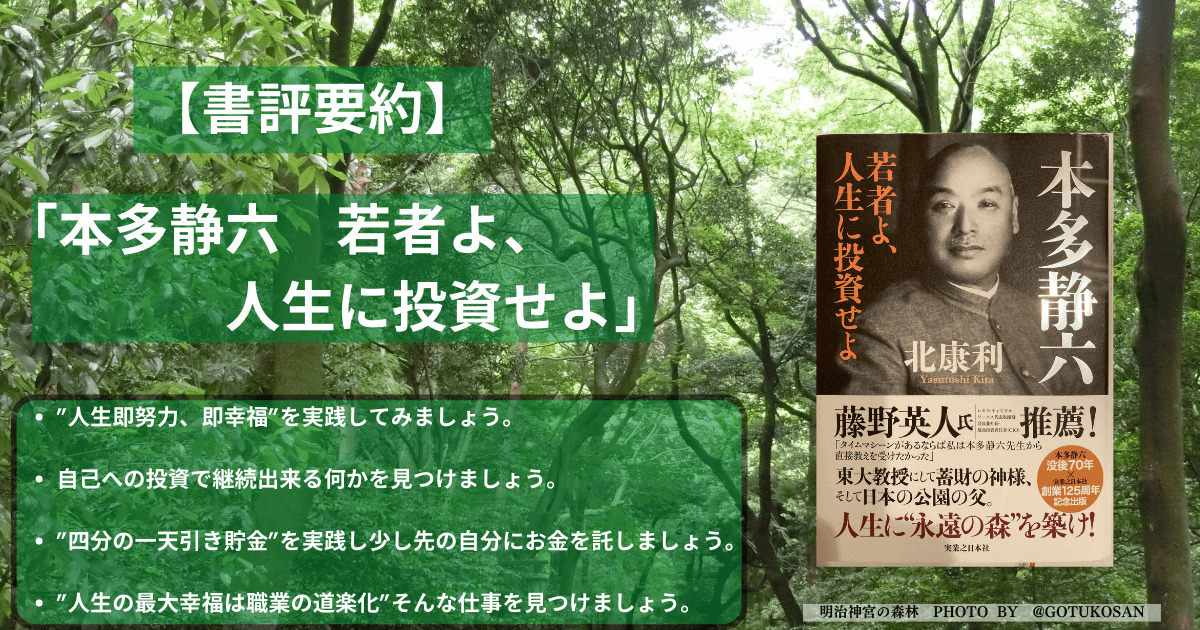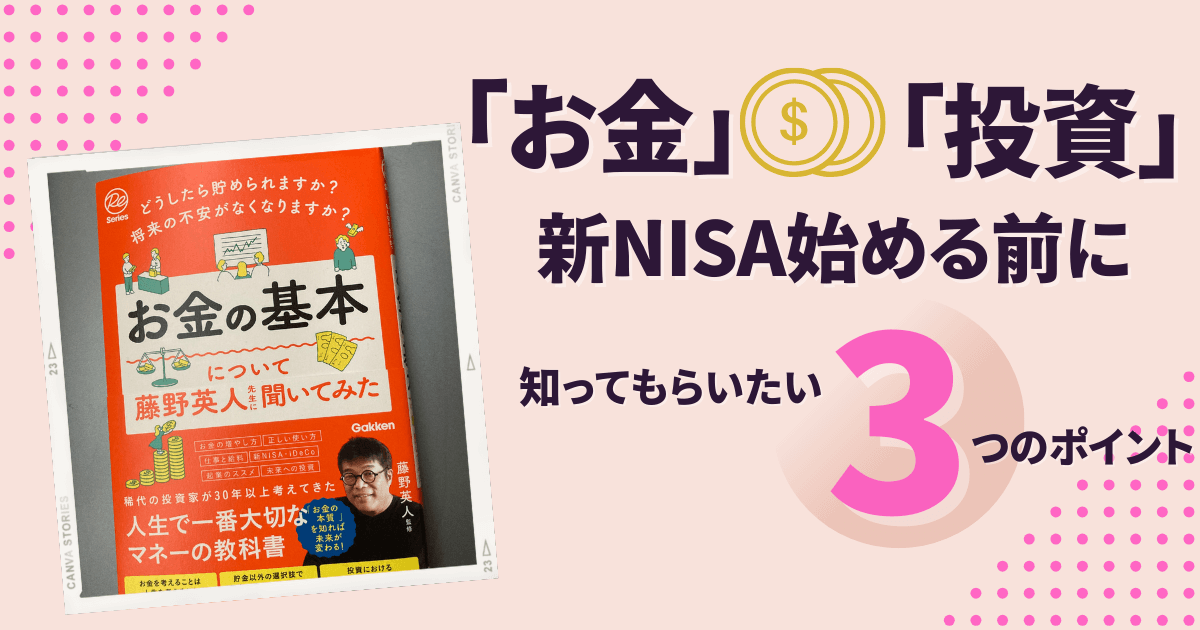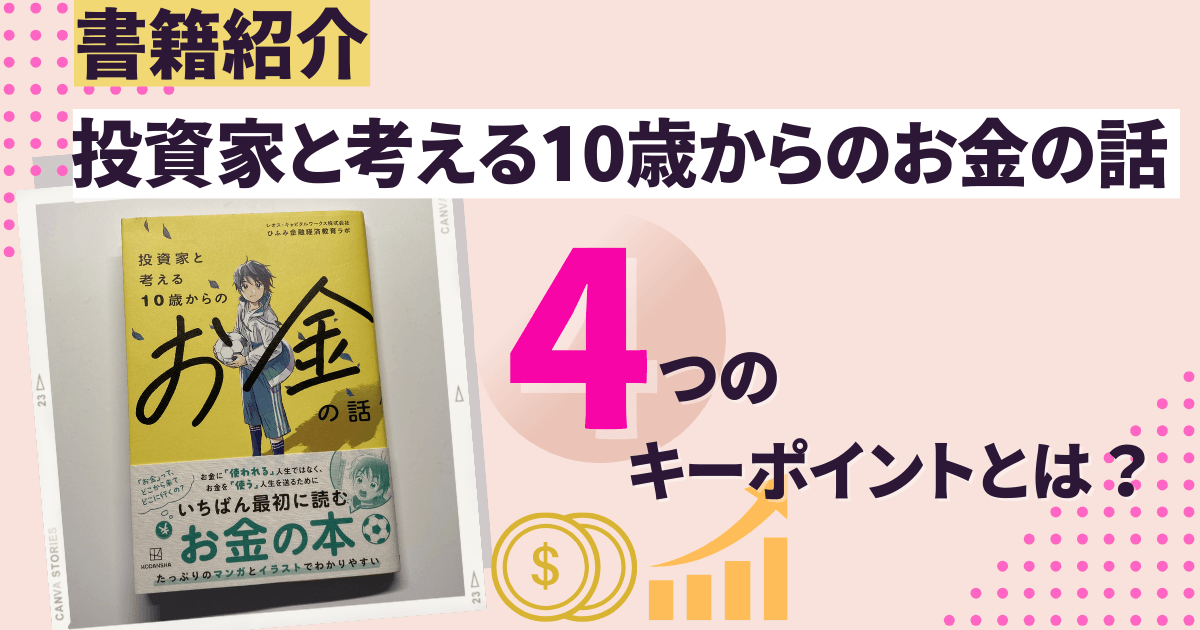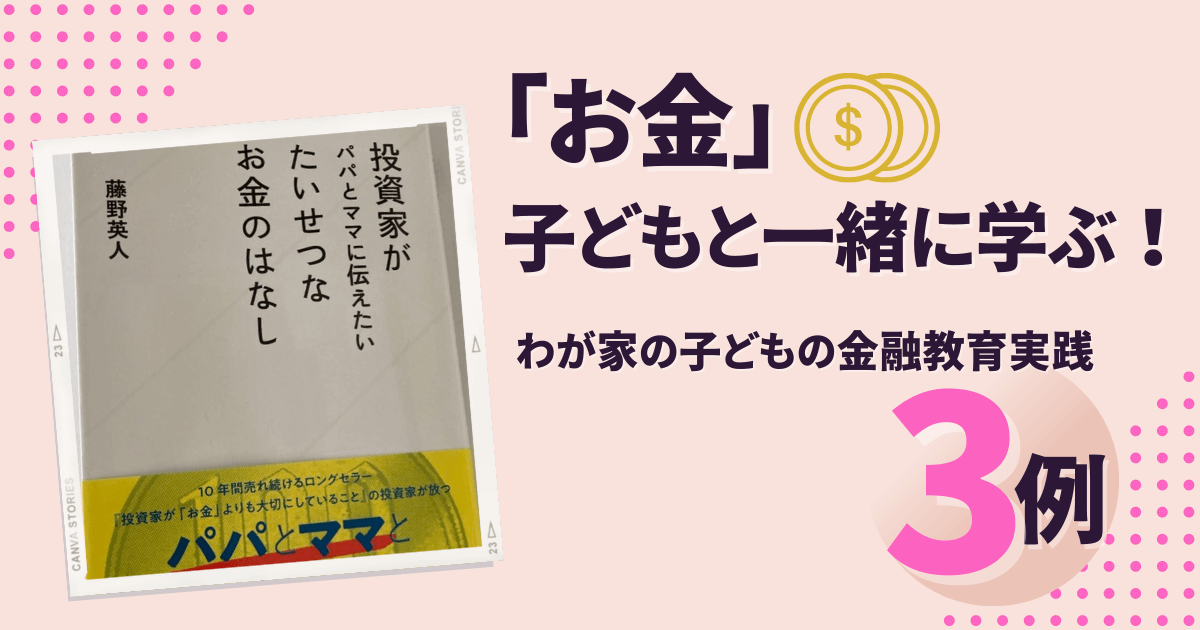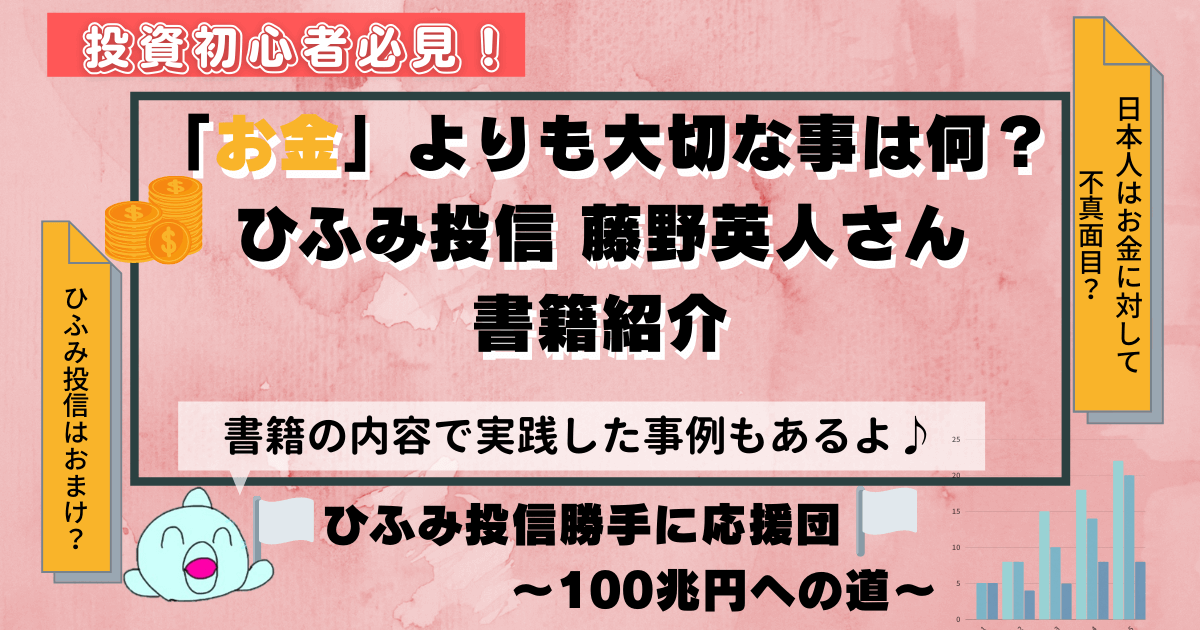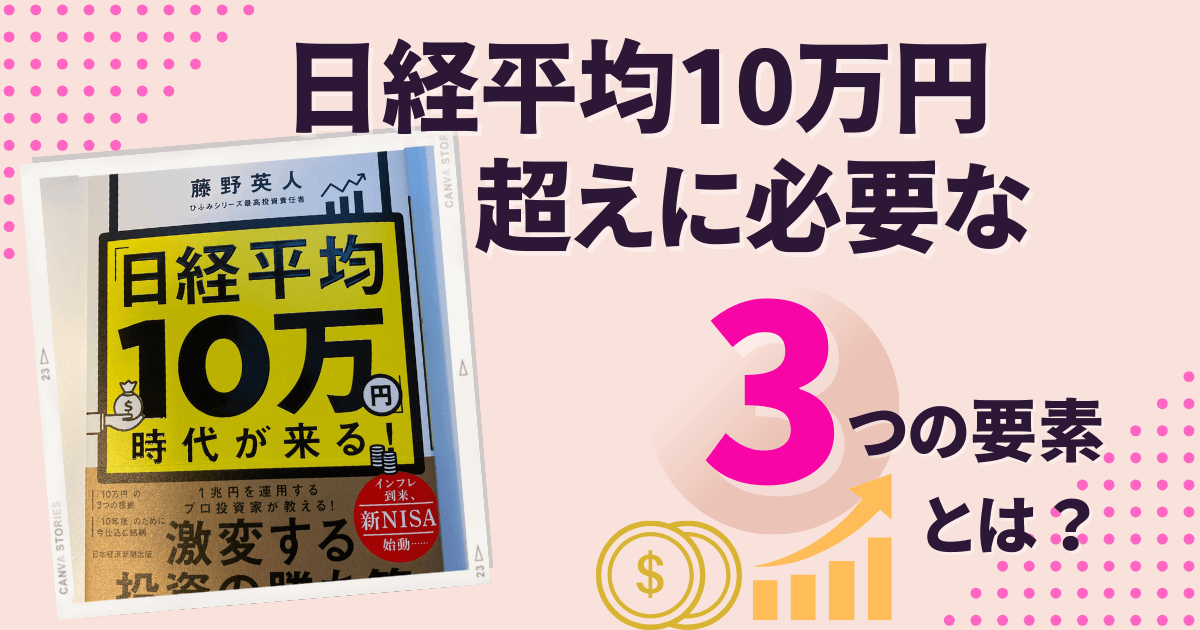インフレ時代の資産形成に必読!福室光生著『投資は金利が9割』レビュー
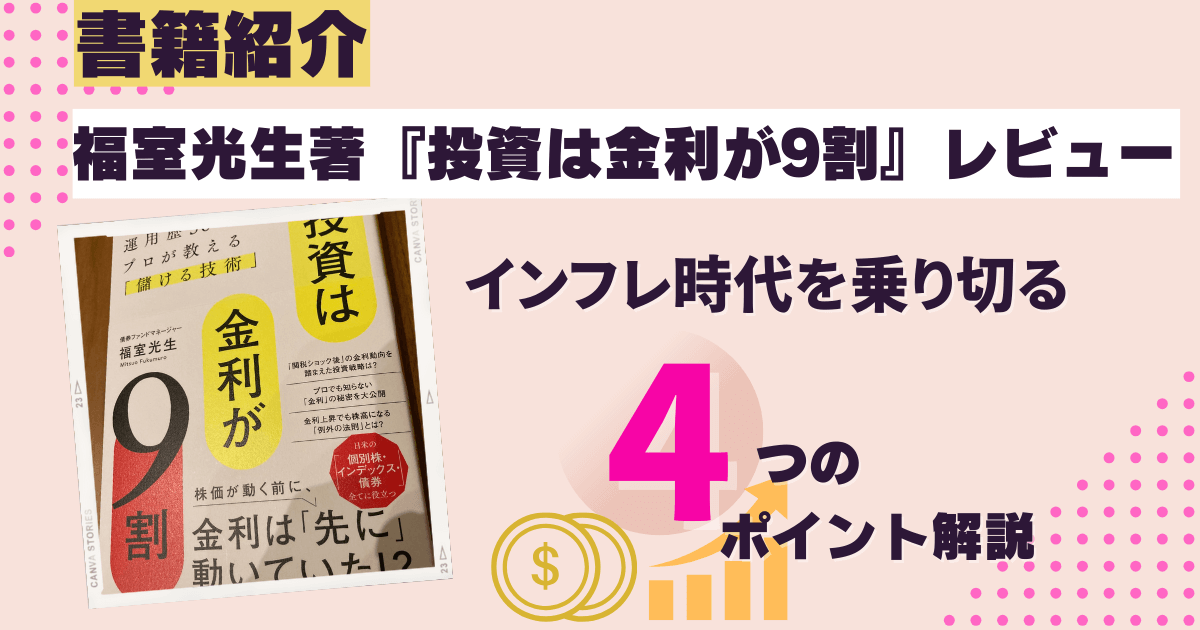
30年続いた日本のデフレ時代は終焉を迎え、コロナ禍をきっかけに日本も本格的なインフレ時代へ突入しました。
ここ数年の物価の高騰や、政府による企業への賃上げ要請など、インフレ時代になってきた実感を日々感じているのではないでしょうか。
そんな時代を私みたいな一庶民が生き残るためには、「金利」を味方につけて、現金を極力持たずに、株や債券、不動産、現物資産などで物価上昇率を超える利回りを維持する必要があります。
今回紹介する書籍は、債券運用のプロが、投資初心者にもわかりやすくかつ、資産形成に役立つ投資と金利と債券の知識を解説してくれている書籍になっております。
また、国債という国が発行する債券を通じて日本という国家の財政事情を読み解く良い勉強にもなり、今後の政治的な判断をする場合の参考になる書籍ともなっております。
この書籍を読むことで、あなたの資産形成にプラスになる一助になると確信しています。
書籍の概要と著者紹介
著者紹介
著者の福室光生氏は、投資信託「ひふみ」シリーズで有名なレオス・キャピタルワークス株式会社の運用本部 債券戦略部長です。
投資信託「ひふみ」シリーズ内のひふみグローバル債券マザーファンドを運用しているファンドマネージャーです。
債券ファンドとは、世界中の国債、社債、地方債などを組み合わせて一つの商品にして受益者に提供するファンドのことです。
福室光生氏はレオス・キャピタルワークス株式会社に所属する前はモルガンスタンレー証券やUBS証券などで債券トレーダーとして長年活躍されておりました。
云わば、債券の超プロフェッショナルです。

レオスの広報の方が、福室さんは知識量は物凄い!と、言ってました。
日々金利や債券について考えている方が、「金利」や「債券」や「投資」についてどのように説明しどのような考えを持っているのか楽しみです。
あらすじ
書籍の目次は以下の通りです。
- 序章:金利で得する人・損する人「5つの分かれ道」
- 第1章:債券と為替の動きが見える「金利の基礎」
- 第2章:異次元緩和の終わりが迫る「国債を買うのは誰?」
- 第3章:お金を守る力が身につく「インフレと円預金の残酷な現実」
- 第4章:国の借金の行く末「財政とお金の見えざる循環」
- 第5章:金利は本当に上がるのか?「株価と財政拡大の読み方」
- 終章:トランプ再選後の米金融市場の動き
序章から3章までは、「金利」「債券」「国債」「投資(運用)」についての基本的や考え方をやさしくレクチャーしてくれており、非常にわかりやすく、かつ、債券ファンドマネージャー視点での株式投資のメリットを伝えてくれるので納得感が非常にあります。
第4章から第5章については、「金利」「国債」についてさらに詳しく、また本質を知る内容になっています。
また、「MMT派」「財政緊縮派」「タームプレミアム」といった聞きなれない単語も随所に飛び交い難解度を上げています。
ただし、この書籍の内容は日本国民すべてが知っておくべき内容だと感じます。
おすすめポイントと共にその理由を解説していきます。
本書から学べる4つのポイント
日本の過去の金融政策から学び、未来の金融政策を考えることでマクロな視点では政治経済への関心度が上がり、ミクロな視点では自身の資産形成の強い味方になります。
ここからは、この書籍のおすすめポイントを4つ紹介します。
一番のポイントは、「お金は消えずに循環する」
私がこの書籍で一番重要だと思ったポイントは、以下の文章だと思いました。
「お金は一方的に消えてなくなることはなく、経済の中を循環している」
誰かの消費は誰かの利益。政府が国債を発行して調達したお金で企業が仕事を請け負いお金が入る。そのお金は個人の給料や銀行預金巡り、銀行は預金の一部は貸出して利ザヤを得る。余ったお金は国債を買う。
この一連の流れでお金は循環しているという考え方を念頭に置くことで、書籍の内容の解像度がぐっと上がった感じがしました。

じゃあ、お金ガンガン刷ってもいいんだ。と思ったかもしれませんが、国の信用など様々なことが絡み合ってくるので、詳しくは書籍を読んでみてね。
「金利の基礎」を学ぶことで損せずに資産形成することができる
私たちが生活していく中で、金利は生活の様々なところで出てきます。
- 住宅ローン金利
- 自動車ローン金利
- カードローン金利
- 銀行預金金利
- 保険の予定利率
などなど、金利を制する者は資産形成を制すると言っても過言ではないくらい重要な点になります。
この書籍では金利についての基本的な知識と、日々の生活で意識すべき場面ごとにどのように金利について考えていけば良いのかをアドバイスしてくれています。

例えば貯蓄性の保険を検討する場合に考えるべき「予定利率」という考え方。年利に換算すると意外に利率が低いという認識を持つことが出来ます。
デフレからインフレへの転換を学ぶ
恐らく、日本中のだれもが感じているであろう、昨今の物価上昇が賃金上昇に追い付いていない現状に将来への不安が広がっているのではないでしょうか。
1990年代初頭のバブル崩壊後、失われた30年と言われたデフレ経済が続きました。ダイソーやユニクロ、ニトリ、ドン・キホーテなどの「薄利多売のビジネスモデル」の企業が躍進した時代が終焉を迎えようとしています。
そして、コロナ禍以降、いわゆるインフレ市場に転換しました。
インフレ草創期は、円安ドル高からの「コスト・プッシュ・インフレ(供給インフレ)」が先行してきましたが、これからは、「ディマンド・プル・インフレ(需要インフレ)」になり、さらに物価は高騰することでしょう。
2025年7月に実施された参院選において、政権与党の自民党が過半数割れし、衆参両院で過半数割れしたことで今後の政治経済がどのような方向に向かうのが良いのか、投票権を持っている国民としては悩ましいところなのではないでしょうか。
私も、子育て世代の就職氷河期世代として資産形成行っていく上で、どのような政党に投票したらよいのか毎回迷います。
そして、色々なメディアやSNSを参考にするのですが、難しい単語が良く出てきて理解できないことが多々あります。
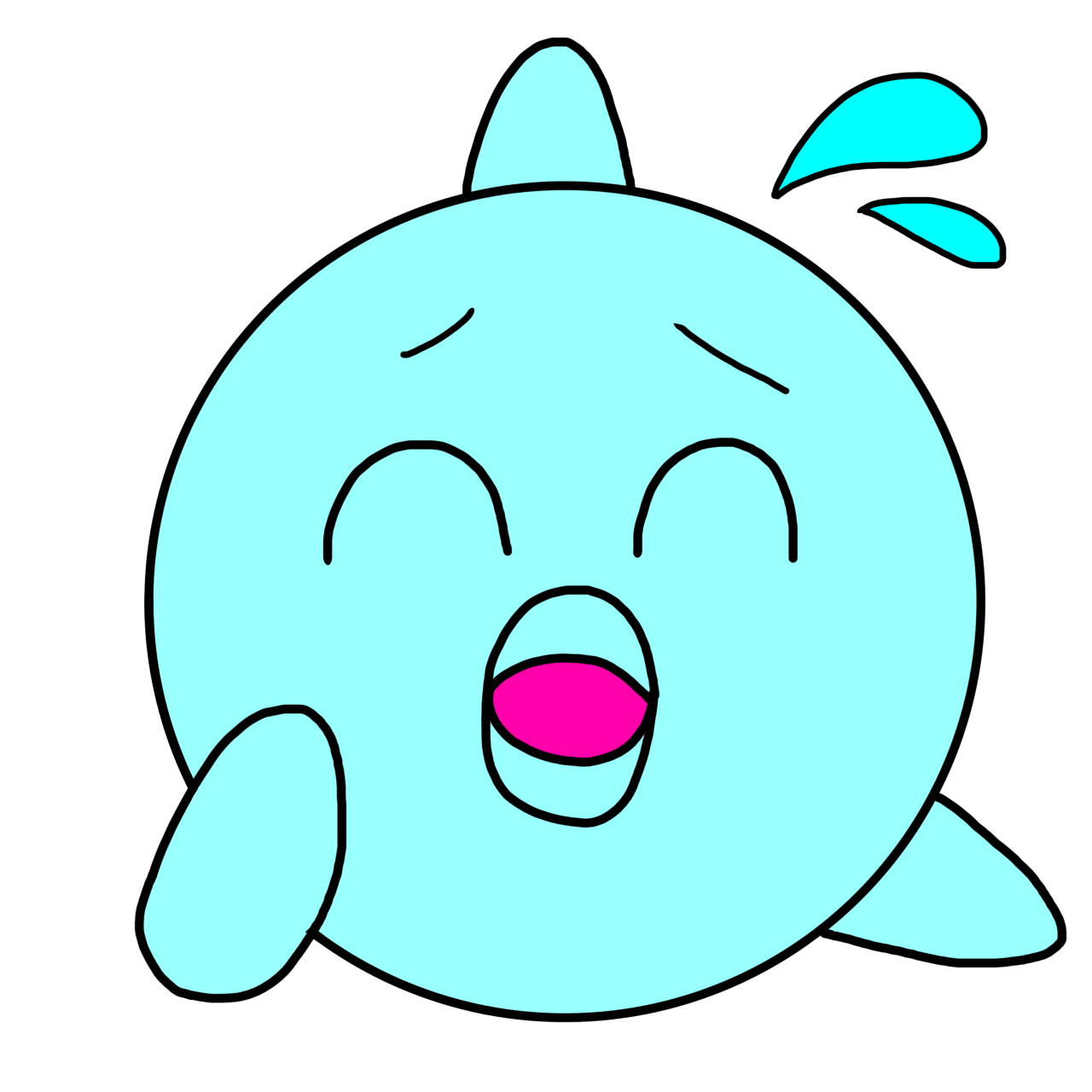
学生時代勉強してこなかったことを今更ながら後悔しています。
例えば書籍の中にも登場する、MMT(モダン・マネタリー・セオリー、現代貨幣理論)、財政緊縮。
なんじゃそれ?
と思いませんか?
私もしっかり理解できている訳でもないですが、今の日本国政では非常に重要な言葉になっています。
MMTとは、自国通貨を持つ国家は通貨発行能力により財政破綻しないという考えから、国債をどんどん刷って、インフレを抑制することで経済は好転するといった考えで、いわゆる積極財政派の思想です。
一方、緊縮財政は国、地方公共団体で、支出の削減、公債の整理などにより予算規模を縮小させた財政のことです。
債券運用のプロが、MMTや緊縮財政について詳しく解説してくれ、かつ、福室さん自身の考えをしっかりと示している点が、今後の投票や国の行く末を考えるのに非常に役立つ内容でした。
債券ファンドマネージャー目線での株式投資のすすめ
福室さんは、国債や社債や地方債などを組み合わせた投資信託を運用しているファンドマネージャーなのですが、そんな福室さんも個人が資産形成するのであれば株式投資を主軸にした運用がおすすめであると書籍では説明しています。
デフレ下では、円預金でも安全かつ高金利の時代がありました。30年前は銀行の普通預金は約6%もありました。
しかし今は、「円預金から出来るだけ逃げること」が必要である。と言及しています。
安定を取るのであれば、金利が0.9%前後の個人向け国債などがおすすめとのことですが、それだけでは物価の上昇率は担保できません。
株式投資をおすすめする理由として以下の2点を挙げています。
- 益利回り
- インフレ
株式投資をすすめる理由の一つ目は、益利回り「一株当たり純利益(EPS)÷株価」という計算式の考え方があります。
株価に対して企業がどれだけ純利益を上げているかということで、PERの逆数になります。
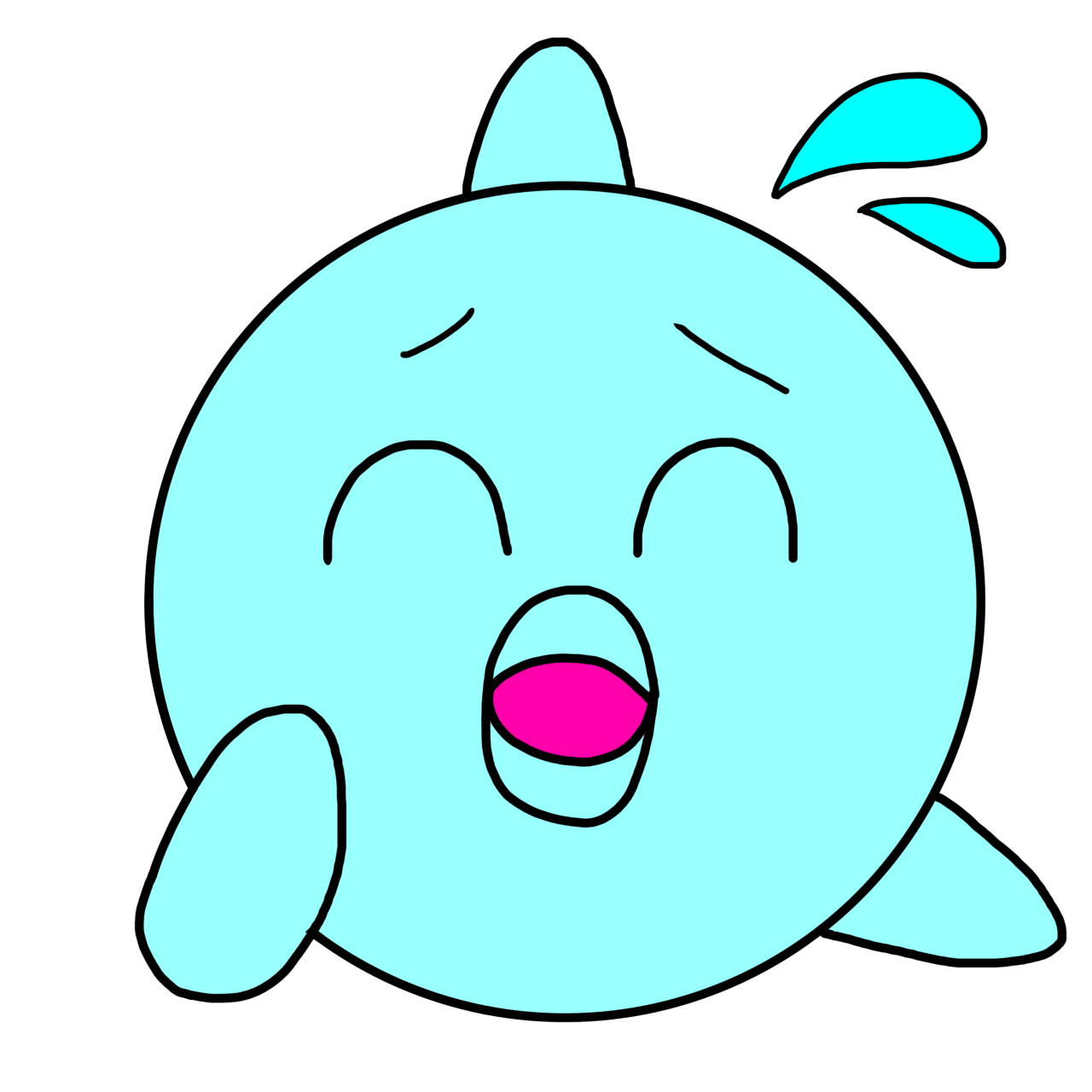
聞いたことがあるようなないような。
米国の2024年益利回りが4.5%だったのに対し、日本株式(TOPIX)は6~7%だったそうです。日本が利上げしてきたとは言え、普通預金の金利はせいぜい0.2%台。
今は米国よりも日本株式の方がリスクを取って株式投資のリターンを得る旨味がある水準なのではないでしょうか。

わたしもひふみ投信や個別株、全世界株式を通して日本の株式に投資しています。
個人的には、日本株式に日本人が投資することで、日本企業の成長による果実を、賃金上昇とともに配当金や株価上昇を享受し、個人資産が増えることで消費も増加するという好循環が起こればいいなと思っています。
つぎに、株式投資をすすめる理由としてインフレです。
インフレ時には企業は製品やサービスの価格を引き上げることで売り上げや利益が増えます。当然株価は企業の利益増を好感し上昇します。
逆に、今日100円で買えたアイスクリームは一年後には物価の上昇により100円では買えなくなります。つまり現金の価値は下がります。
インフレが加速すると、日銀やFRB(連邦準備制度理事会)が物価の安定を促すために金利を上げますが、それでも株式は長期的に見れば右肩上がりになります。
書籍では、やはり王道の全世界の株式指数に連動した投資信託の通称オルカンこと、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をすすめていました。

わが家でも主軸はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)です。
インフレ時代の対策として少額からでも良いので株式投資を始めてみてはいかがでしょうか。
まとめ
本書『投資は金利が9割』は、金利や債券の専門知識を、一般の私たちにも理解できるように解説してくれる一冊です。
- 「お金は循環する」という視点
- 金利を生活にどう活かすか
- 日本の金融政策とインフレへの理解
- 株式投資を主軸とした資産形成のすすめ
これらを学ぶことで、インフレ時代を乗り越えるための判断力が養われます。難しい単語も登場しますが、資産形成や投票行動を考えるうえで必読の書だと感じました。
少額投資からでも、まずは一歩を踏み出す。そのきっかけとして本書を手に取ってみてはいかがでしょうか。